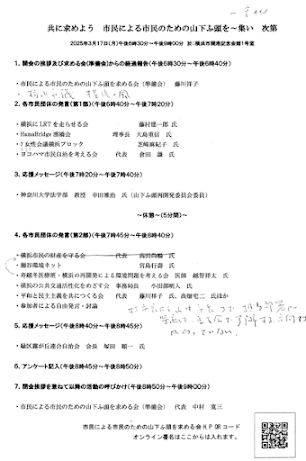先日ウクライナの支援コンサートがあり、ヴァイオリンとピアノのよく知った曲のほかに、神父さんがマイフェアレディの中のMy favorite thingsをジャズ風にピアノで演奏したのち、戦争のあるウクライナから日本に避難をしてきた人たちが合唱を行った。その合唱からは「頑張るぞ!!」という意志がよく伝わってきた。また観客はその意志に気持ちとして共感した。
それと似たような気持ちになったのは、横浜ボートシアターの演劇「小栗判官・照手姫」で、人々がかわるがわる「えいさらえいさらえいさらえい」といいながら餓鬼を熊野に向かって引いていく場面で、聞いている人はそれに対して「生きろ!生きろ!」と聞こえてくる。戦争は人の生死にかかわってくるので切実な感じがよくわかる。
音楽は楽しい感情や悲しい感情を表現することが多く、戦争と音楽は一般的には相反する概念の様であるが、逆に音楽が戦争を遂行する場合もありそうなので、主に戦争を遂行する場合を主に書いてみた。特にリズムに関係しているかも。
最初に浮かぶのは「ハーメルンの笛吹き男」で、ハーメルンで昔 ネズミがはびこって、住民が苦労しているときに、ネズミを退治するので、金貨を一袋くださいと村長に言って了解をえたら、その男が笛を取り出し、町中を歩きネズミを連れ出してくれました。大成功の結果だったが、村長はお金を出し渋ったら、今度は再度笛を吹いて子供たちを連れて行ってしまって2度と戻ってこなかったと言うことです。小さなころ話を聞かせられて、言うことを聴かないとだれかが連れて行ってしまうよと脅された。おとぎ話としてはいい効果があったかもしれないが、何となく恐ろしい話で、何らかの戦争が影響しているような気がする。どんな音楽かは分からないがとにかく聞きほれるような美しい音色ではなく、人を動かす規則正しいリズムのような感じではないかと思う。
童謡の「鉞担いだ金太郎」は、鉞(まさかり)は丸太を削る道具だし、クマにまたがりお馬の稽古も、子供の元気な様子を描いているようだが、とにかく戦いのためには勇ましいことがいいという方向を示しているようにみえる。
乱拍子は、白拍子というリズムのそろった拍子に対して、リズムを乱して表現する方法で、13世紀、歌謡および舞にて拍子のついた白拍子・乱拍子が流行した。今では乱拍子という言葉は能では唯一残っているのは、道成寺のシテの白拍子が舞う踊り方で、足の使い方に特徴がある。実は身近な驚神社の祭りのお囃子の中にも一歩一歩笛を止めるような乱拍子という笛の吹き方がある。乱拍子の流行った時代は、保元・平治の乱に始まる源平合戦や南北朝の内乱、応仁の乱、そして戦国時代と戦乱がつづく時代だったので影響を受けたような気がする。
白拍子と乱拍子というブログ(http://yab-onkyo.blogspot.com/2022/05/blog-post.html)2022.05.04に示している。
陣太鼓は多分戦国時代に、戦の合図に用いられたものをいうので、戦争に深く関係しているが、現在はこの和太鼓は御陣乗太鼓(能登の名舟のごじんじょだいこ)や鬼太鼓座(おんでこざ)などで音楽として活躍している。最近の和太鼓はリズムのノリがいい感じだ。
軍楽隊の始まりである鼓笛隊は安政3年(1856年)に長崎海軍伝習所で、オランダ人から艦船の操縦法とドラムのレッスンが始まった。最も古い鼓笛譜が、安政3年(1856年)に「西洋行軍鼓譜」として出版された。その数年前、嘉永6年6月3日(1853年7月8日)アメリカのペリーが1852年11月24日東海岸を出発し、大西洋、南アフリカ経由で浦賀沖に現れた。安政元年3月3日(1854年3月31日)日米和親条約、安政5年6月2日(1859年)日米修好通商条約締結、安政6年6月2日(1859年7月1日)横浜開港。(2009年横浜開港150周年記念祭)。当時アメリカでは1861年から1865年まで南北戦争。世の中は動乱が始まったようだ。明治2年に薩摩藩は横浜へ三〇余名の青年を送り、イギリス海軍第10連隊の軍楽長フェントン(John Williams Fenton)から伝習を受けさせた。この軍楽手を中心に、明治4年5月、明治政府 兵部省は各藩の鼓手を加えて軍楽隊を創設した。これに先立ち1870年(明治3年)、イギリス公使館護衛隊歩兵大隊のジョン・ウィリアム・フェントンによって最初の「君が代」が作曲された。フェントンに作曲を依頼したのは薩摩藩。音楽のリズムによって、全体の大きな軍隊が一体の動きをすることができることは、場合に寄っては長所でもあるが、一糸乱れずの動きは横から見ると不安になる。このフェントンの作曲した君が代は、古今和歌集の君が代と合わなく、現在の君が代は宮内庁の雅楽課の人たちからの公募で、フランツ・エッケルト(ドイツ)が伴奏を付けて雅楽課の林廣守作曲と言うことになったようだ。歌詞のもともとは古今和歌集からとったようで、勇ましい感じの曲ではない。今ではお相撲やスポーツの国際大会の時に演奏されるのを聴いているが、どちらかといえば、しっとりとした落ち着いた曲のようで、勇ましい曲ではないと感じる。
ヨーロッパで始まったクラシック音楽はドイツで始まり、ウィーンで花開き、東欧に重心が移動し、さらにサンクトペテルブルグに移動しているように感じる。チャイコフスキーはサンクトペテルブルグの大学で法律の勉強をしたのち、音楽に転向し、モスクワで活動をした。
ヨハン・セバスチャン・バッハ(1685~1750)はドイツのライプッチィヒで活躍した。ゲオルク・フリードリヒ・ヘンデル(1685~1759)はドイツのハレで生まれイギリスで活躍した。バロック時代の作曲家となり、その後はクラッシック音楽の中心ウィーンに移動する。フランツ・ヨーゼフ・ハイドン(1732~1809)、ヴォルガング・アマデウス・モーツアルト(1756~1791)、ルートヴィッヒ・ヴァン・ベートーベン(1770~1827)、フランツ・シューベルト(1797~1828)などウィーンを中心に動いていた。フレデリック・ショパン(1810~1849)はポーランド生まれで、やはり主にウィーンで活躍した。ロベルト・アレキザンダー・シューマン(1810~1856)ドイツ、フランツ・リスト(1811~1886)ハンガリー生まれ、ヨハネス・ブラームス(1833~0897)ハンブルグ生まれ、アントニン・ドヴォルザーク(1841~1904)ボヘミア プラハ近郊生まれ。グスタフ・マーラー(1860~1911)チェコ、映画「ベニスに死す」の交響曲5番で甘美なメロデイーで有名、今までの曲は人間の気持ちや意志を表現するような曲であったが、次第に映像的なメロデイーに変化していき、しかも作曲の中心がロシアに移動し始める。以降はロシアの作曲家を上げる。ムソルグスキーは「展覧会の絵」で有名であるが、やはり絵画的で感覚的なメロデイー、チャイコフスキーも「白鳥の湖」や「くるみ割り人形」でロマン的な美しく、華やかなメロデイー、ラフマニノフも美しいメロデイー。アレキサンドル・ボロディン(1833~1887)、モデスト・ペトローヴィッチ・ムソルグスキー(1839~1881)、ピョートル・イリイチ・チャイコフスキー(1840~1893)、リムスキー・コルサコフ(1844~1908)、セルゲイ・ラフマニノフ(1873~1943)、イーゴリ・ストラビンスキー(1882~1971)、セルゲイ・プロコフィエフ(1891~1953)、ドミートリ―・ショスタコーヴィッチ(1906-1975)、アルフレート・シュニトケ( 1934~1998))。チャイコフスキーが活躍していたころは明治元年(1868)ごろで、世の中が落ち着かない状態となっていることがわかる。その後 第1次世界大戦が1914年に起こり、ロシアでは1917年2月にサンクトぺテルベルクで帝政が崩壊し2月革命が起きたが、その後、社会主義革命として、10月革命が起きた。1934年はスターリンの大粛清があった年である。ショスタコーヴィッチは1906年に生まれ、この10月革命は生まれた後におきた。家庭画報.comには「ソ連体制下での危機から作曲者を救った名曲」とあり、「最も人気が高く、頻繁に演奏される『交響曲第5番』は、スターリン体制下のソ連において、窮地に陥ったショスタコーヴィチを救った名作です。オペラ『ムツェンスク郡のマクベス夫人』などが体制の意向に外れた作品であると批判されたショスタコーヴィチは、この批判を素直に受け止め、古典へ回帰した作品を生み出すことに全力を注いだのです。その結果生まれた作品『交響曲第5番』は絶賛され、ショスタコーヴィチの危機を救うとともに、その名を全世界に広めるきっかけとなったのです。」オペラ『ムツェンスク郡のマクベス夫人』は1936年、この交響曲5番は1937年作曲で、大砲が打ち合う激しく勇ましい感じの音と悲しそうな部分が混ざっており、一見戦争を遂行する激しい音とリズムで、体制を支持している反面、悲しそうな部分で反戦の気持ちを表しているような内容で作曲家が苦労したことが何となくわかるような曲である。またショスタコヴィッチは交響曲7番レニングラードという曲で、ナチスがレニングラード(現 サンクトペテルブルグ)を数年間包囲したときに、レニングラードで演奏し、住民を鼓舞したことでも知られている。静かな部分と戦いを始めるような部分である。これを聴くと、ラベルのボレロを思い出す。民衆の戦いが深くさらに広がっていく様子が描かれているようだ。
John LennonのIMAGINEという曲も、音がまるでランダムに機関銃を打っている音に聞こえる。多分戦争を想像してみろ!という曲だろうと思う。けっしていいことは無いぞと宣言している感じだ。
音楽と戦争に対して、さまざまな場合を書いてきたが、正確に言えば、戦争に対して音楽の音色やリズムはそれぞれ関係があるともないともいえる。それよりは、結局作曲者の意志に関係することが最も大きいかもしれない。今後ともウクライナやパレスチナのコンサートがあれば、生きろ、生きろと応援したくなると思う。
古代エジプト展についての記事が朝日新聞に載った。私もここに見に行ったが楽器についての遺跡は見当たらないと思っていたが、石板に彫刻されていたのがあったようだ。内容は王が女神に楽器で何らかのことを多分平和や豊作をお祈りしていたような気がする。音楽はどちらかといえば、戦争より、このような目的の方が似合った感じだ。
2025.03.06 朝日新聞朝刊の古代エジプト展の記事