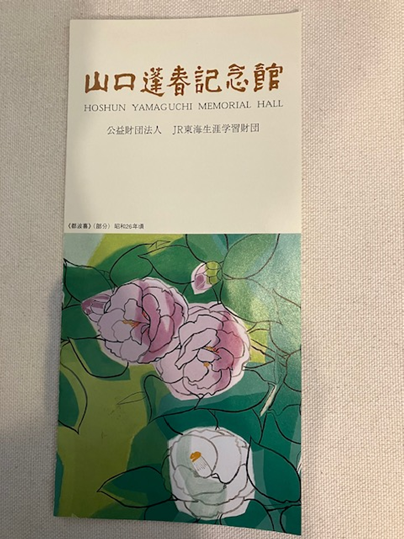16世紀後半には、シェークスピアやセルバンテス、オペラ、歌舞伎、人形浄瑠璃、クラシックのオーケストラ、さらに京劇などがほぼ同時期に成立した。この時代、アラブやインド、アフリカ、東南アジア、中国、朝鮮、ロシアなどではどんなことがあったかよくわかっていないが、ユーラシア大陸の西の端のイギリスやスペインと東の端の日本との間にはたくさんの国々があり、まだ調べられていない出来事があるに違いない。この建築音響の交流の歴史その3では、アラビアンナイト、西遊記、弦楽器のリュート、歌舞伎や人形浄瑠璃、京劇、1600年ころの科学技術、クラシック音楽、ハンマーのピアノの発明、純正律以降の音律、朱載堉の「律学新説」、和算家の中根元圭の「律原発揮」を挙げた。アラビアンナイトはイスラムの人々が交易民で、世界に交流があった。西遊記は、唐の時代にインドまで行って仏教を取り入れたことを、演劇的に構成し、世界的に広めた。リュートはペルシャで発祥したが、ヨーロッパでリュート、ウイグル、さらに日本の奈良時代に運ばれ、琵琶となったようだ。歌舞伎や人形浄瑠璃は京劇と同じく17世紀前半にできて、シェークスピアやセルバンテスやオペラなどの演劇と一緒にこの時代に創生された。また1600年ごろから始まったコペルニクスやガリレオやニュートンなどにより科学技術が発展したが、これはヨーロッパの世界への航海と連動しているようだ。ヨーロッパのクラシック音楽も17世紀ごろから発展してきた。それまで音楽は多分自然を対象に表現してきたが、科学技術の発展があり、教会での純正律や中全音律が開発され、ドミソの美しい和音ができるようになったことと相まって、クラシック音楽が人間の感情を表現するように発展してきたものと思われる。12平均律は1636年にメルセンヌによって開発されたが、19世紀になって、転調の容易さから純正律や中全音律にとってかわられるようになってきた。またこの12平均律は、中国でも1584年に朱載堉が、また1692和算家の中根元圭が発表をしている。16世紀ごろにおいても、地球規模で音楽や演劇や科学技術が、かなり連動して動いているような気がする。また馬場良始(数学者)が書いたヨーロッパの純正律以降の音律の流れはちょっと建築音響の交流と離れてしまうが、純正率が出来た過程とその後の12平均律が出来てくるまでを細かく書いているので、長くなってしまったが引用させていただいた。ただ12平均律の現在への変遷については、ちょっと横目で見ている感じである。また和音等についての考え方は、多分人間の社会に対する考え方が影響しているように思い、今後音楽がどのように変化していくかも課題だと思う。今は特に地球の環境や自然をさらに表現する必要があり、そのために音律がどうあるべきかは今後の大きな課題ではないかと思う。
9世紀ころ、アラビアンナイトの原型ができた。
多くの謎を秘めた物語 「アラビアンナイト」 ゲスト講師 西尾哲夫より抜き書き引用
『「アラビアンナイト」はまたの名を「千一夜物語」といい、洋の東西を問わず、年齢を問わず親しまれている文学です。その原形ができたのは九世紀ころといわれ、日本でいえば平安時代にあたります。
世界を見回せば、アラビアンナイトと同時代に生まれた文学はたくさんあります。この日本にも少し時代はくだりますが、『源氏物語』や『伊勢物語』のような名作があります。』 『アラビアンナイトにはイスラームの人びとが歴史の中で培ってきた文化や宗教観がたっぷりと込められていますし、すぐれた交易民であったゆえのグローバルな精神も随所に垣間見ることができます。』
歌舞伎:出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』を参考にした。 『1603年(慶長8年)ころ、京都で出雲阿国が始めたややこ踊り、かぶき踊り(踊念仏)が始まりで江戸時代に発展し、女歌舞伎から若衆歌舞伎、野郎歌舞伎と風俗紊乱を理由とした規制により変化していった。またこのころのこの頃の歌舞伎は能舞台で演じられていたようだ。』 『江戸四座(後述)のうち格段に早くに成立した猿若勘三郎座を除き、それ以外の三座が安定した興行を行えるようになったのも寛文・延宝の頃である。[』] ※寛文1661~1673、延宝1673~1681『元禄年間を中心とする約50年間で、歌舞伎は飛躍的な発展を遂げ、この時期の歌舞伎は特に「元禄歌舞伎」と呼ばれている。[』
人形浄瑠璃17世紀初期:文楽協会のホームページより引用
『人形浄瑠璃文楽は、日本を代表する伝統芸能の一つで、太夫・三味線・人形が一体となった総合芸術です。その成立ちは江戸時代初期にさかのぼり、古くはあやつり人形、そののち人形浄瑠璃と呼ばれています。竹本義太夫の義太夫節と近松門左衛門の作品により、人形浄瑠璃は大人気を得て全盛期を迎え、竹本座が創設されました。この後豊竹座をはじめいくつかの人形浄瑠璃座が盛衰を繰り返し、幕末、淡路の植村文楽軒が大阪ではじめた一座が最も有力で中心的な存在となり、やがて「文楽」が人形浄瑠璃の代名詞となり今日に至っています。』
京劇(きょうげき、けいげき、拼音: Jīng jù ジンジュウ)は、中国の伝統的な古典演劇でもある戯曲(歌劇の一種のこと)の一つ。楽器は二胡 京胡 月琴 銅鑼・大鑼小鑼、打鼓 小鼓・単皮鼓 嗩吶 哨 三弦 鐃 鈸
清の乾隆55年(1790年)、中国南方の4つの徽劇班「三慶班」「四喜班」「和春班」「春台班」(四大徽班)陸続と北京に来訪。まず「二黄」声腔を持ち味とする「三慶班」が北京で人気を博し、それに続いて「四喜班」「和春班」「春台班」が北京に進出した。北京には「秦腔」という演劇があったが安徽省の劇団に人気を奪われる形となり、両者の融合が自然と行われた。道光8年(1828年)前後、湖北劇団が北京に進出し漢調(楚調・西皮調)を特色とした演劇は安徽省発祥の劇団にも影響を与え、独自の演劇へと発展して行った。このように北京の外の劇団が担ってきた北京の演劇であり上演は南方方言で行われてきたが、北京での人気を得るに従い北京語での演劇の需要が高まり、北京語での演劇が考案、上演されるようになった。近代において一番京劇に悪影響を与えたのが文化大革命による弾圧で幹部俳優が排斥されたり、古典劇の上演が禁止されるなど停滞した。この弾圧は江青が現代劇の俳優出身で、京劇を目の敵にしていた事が原因と言われる。その後、中国の伝統文化として見直され「国劇」と呼ばれるように至った。
※京劇は歌舞伎の開始より多少遅いが、ほぼ同時期に成長した。また京劇の前段階の演劇はあると思われる。
1600年ごろの科学技術:ニコラウス・コペルニクス( 1473 - 1543)晩年に『天球の回転について』を著し、当時主流だった地球中心説(天動説)を覆す太陽中心説(地動説)を唱えた。ティコ・ブラーエ (1546-1601)、ガリレオ・ガリレイ(1564~1642)力と運動の力学、ヨハネス・ケプラー(1571- 1630)、ドイツの天文学者。天体物理学者の先駆的存在、ニコラウス・コペルニクスやティコ・ブラーエ、ガリレオ・ガリレイも脱却できなかった円運動に基づく天体論から、楕円運動を基本とする天体論を唱え、近世自然哲学を刷新した。さらにニュートン(1642~1727)のプリンキピア1686、ライプニッツ(1646~1716)の微積分法。オイラー(1707~1783)数学者オイラーの定理など、ダランベール(1717~1783)物理学者ダランベールの原理、ベルヌーイ(1700~1783)理想流体のエネルギーが保存されることを示したベルヌーイの定理、ラグランジェ(1736~1813)数学者 解析力学、ラプラス(1749~1827)数学者、天体力学概論と確率論の解析理論、ルジャンドル(1752~1833)数学者整数論 楕円積分、フーリエ(1760~1830)物理学者フーリエ解析を用いいて熱伝導方程式を解く、ポアソン((1781~1840)数学者ポアソン分布、関孝和(1640(またはニュートンと同じ1642)~1708 行列式の解法(解伏題之法1683)、方程式の解法(解隠題之法1685)、暦について(二十四気昼夜刻数1699)
1636メルセンヌの音楽総論 Marin
Mersenne(1588~1648)科学的音響学の草分け、1640年ころ音の反響と振り子時計を使って初めて音速を316m/sと測定。ヨーロッパにおいて12平均律の確立、
17世紀にはクラシック音楽が始まっている。ビバルディ(1678~1741ベネチア)、ヨハン・セバスティアン・バッハ(1685~1750、ドイツ)、ヘンデル(1685~1759 ドイツのハルレのちイギリスに帰化)、グルック(1714~1787南ドイツ)、ハイドン(1732~1809 オーストリア)、モーツアルト(1756~1791オーストリア ザルツブルグ)、ベートーベン(1770~1827 ドイツ ボン)、ウエーバー(1786~1826 北ドイツ、ロッシーニ(1792~1868 イタリア)、フランツ・シューベルト(1797~1828 ウイーン)、ベルリオーズ(1803~1869 フランス リオン)、メンデルスゾーン(1809~1847 ドイツ)、シューマン1810~1856 ドイツ)、ショパン(1810~1849 ポーランド)、リスト(1811~1886 ハンガリー)、ワーグナー(1813~1883 ドイツ)、ベルディ(1813~1901 イタリア)、スメタナ(1824~1884 チェコスロバキア)、フランク(1822~1890 ベルギー)、ブルックナー(1824~1896 オーストリア)、ヨハンシュトラウス(父)(1804~1849)、ヨハンシュトラウス(子)(1825~1899)、フォスター(1826~1864 アメリカ)、ブラームス1833~1897 北ドイツ ハンブルク)、ボロディン(1833~1887 ペテルスブルグ)、サン・サーンス(1835~1921 フランス)、ビゼー(1838~1875 パリ)、ムソルグスキー(1839~1881 ロシア)、チャイコフスキー(1840~1893 ロシア)、ドボルザーク(1841~1904 ボヘミア)、グリーグ(1843~1907 ノルウエ―)、サラサーテ(1844~1908 スペイン)、リムスキー・コルサコフ(1844~1908 )、フォーレ(1845~1924)、プッチーニ(1858~1924イタリア)、ウォルフ(1860~1903 オーストリア)、マーラー(1860~1911 ボヘミア)、ドビュッシー(1862~1918 フランス)、リヒャルト・シュトラウス(1864~1949 ドイツ)、シベリウス(1865~1957 フィンランド)、スクリャーピン(1872~1915 モスクワ)、ラフマニノフ(1873~1943 ロシア)、シェーンベルク(1874~1951 ウイーン)、ラベル(1875~1937 フランス)、ファリア(1876~1946 スペイン)、レスピーギ(1879~1936 イタリア)、バルトーク1881~1945 ハンガリー)、ストラビンスキー1882~1971ソビエト)、プロコフィエフ(1891~1953 ロシア)、グロフェ(1892~1972 ニューヨーク)、ハチャトリアン(1903~1978 ソビエト)、ショスタコービッチ(1906~1975 ソビエト)、ブリトン、イザイ、ヒンデミット、パガニーニ、アルチュール・オネゲル、ミヨー、レスピーギ、アルベニス、コダーイ、ガーシュイン、武満徹、アミルカレ・ポンキエッリ(1834~1886、ラ・ジョコンダ作曲1876年)、ペールギュント (ヘンリック・イプセン1867年戯曲、エドヴァルド・グリーグ1875年作曲)
16世紀後半、織田信長(1534~1582)日本で始めて西洋音楽を聴いた日本人の一人、曲はおそらくアヴェ・マリアなど、楽器はポルタティーフ・オルガン、バロック・バイオリン、ビオラ・ダ・ガンバ
15世紀、スペインのバルイトロメー・ラモスは純正三度の5/4の比率を含む純正調という名の音律を考案した。この音階ではピタゴラスの音階もいくつか含まれているが、第三度音(5/4)、第六度音(5/3)、第七度音(15/8)が決定的な違いがある。ルネッサンスの気運。十字軍がトレドにあるアラブの図書館を奪還して、作曲家のツァルリーノは中からプトレマイオスの「和声論」のテトラコードに出会い、ラモスの音律と同じあることを発見した。また和声的な分割方法はモノコードの操作を通じて、倍音の存在が予見されていた。
1523、ピエトロ・アーロン(1480~1545)、イタリアの作曲家、ミーントーン(中全音律ともいう)を発表。ミーントーンでは三度をいかに純正な音程(5/4)に保つために純正五度の音程をすこしだけ狭くしたもので、唸りのない純正音程を微妙にずらすことをテンペラメント「Temperament」という。ミーントーンでは適用できる調の範囲も広がり、協和と不協和の際立った関係の中に置くと、「感情過多様式」と呼ばれるバロック末期の独特のスタイルが生み出される一因となった。ヘンデルをはじめ、バロック時代の多くの作曲家たちに愛用された。
バッハの平均律クラビーア曲集:原題の"wohltemperierte"とは、鍵盤楽器があらゆる調で演奏可能となるよう「良く調整された(well-tempered)」ことを示し、本来は転調自由な音律を広く意味するが、和訳ではいまだに「平均律」が用いられている.
※以下は馬場良始(数学者)が書いた16世紀以降の音律について、長くなったが、ところどころ引用した。音律の探求(16世紀以降) —小学校専門科目「数学」での実践—馬場良始(ばんばよしとも)大阪教育大学数学教育講座
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.osaka-kyoiku.ac.jp/~ybaba/onritsu3.pdf
『純正とは2音の振動数比が、 1:2 (オクターブ)、 2:3 (完全5度)、 3:4 (完全4度) 、4:5 (長3度)、 5:6 (短3度)、 4:6 (長6度)、5:8 (短6度) であるとき、それらは心地よく協和し、その一点を少しでも外れると協和性は直ちに悪化した。』
『このアイディアは,クラウディオス・プトレマイオス(83年頃~168年頃:古代ローマの数学者・天文学者・音楽理論家)が、ギリシャ時代の音律について書いた音楽理論書にすでに見られる。この本には、ギリシャ時代の音律がたくさん載せられているが、実用性を重んじるローマ時代に、ピタゴラス音律以外の音律は忘れ去られてしまった。その後、バルトロメ・ラミス(1440年頃~1491年頃:スペインの作曲家・音楽理論家)が1482年に発表した「実践音楽」に、再び純正律を意識した音律が表れる。この音律が純正律の基礎原理となった。。このラミスの本以降、急速に3度音程が重要視されるようになり(それまでは、3度音程が不協和なピタゴラス音律が用いれていた)、ラミスの音律がヒントとなって、後で紹介する「中全音律」が1523年にいきなりピエトロ・アーロン(1480年~1545年:イタリアの作曲家・音楽理論家。フィレンツェ出身)によって提唱された。その後、 1529年にフォリアーノによって純正律の半音階的半音が確立される。残響の多い教会で、たとえ単旋律の合唱であっても、前の音が残っている間に3度・4度・5度を取るので自然と純正律で歌っていたと考えられるが、およそ15世紀から16世紀にかけて鍵盤楽器の発展とともに、その純正律を厳密に記述する試みがなされ、このような成果が現れたと見られる。』
『ヴァイオリン奏者の玉木宏樹氏は、ヴァイオリン演奏においてはピタゴラス音律と純正律を使い分けて演奏しており、平均律のピッチで奏くことは考えられない、と述べられている。』
『この頃、名の通った数学者・物理学者はたいてい音律問題に首を突っ込んでいて、かなりの数の提案をしていたが、音楽の現場ではたやすく調律できることが重要であるため、実際に使われていた種類は限られていたようである。ケプラーやオイラーの音律も、残念ながら実践的な意味をもつには至らなかったが、後続の音律研究者達により幾度となく引用・分析され、それなりの存在感を見せている。』
『しかし、先にも述べたように、ラミスの音律が登場し、3度の重要性が増したこともあり、1523年に中全音律が考案された。これ以降ヨハン・ゼバスティアン・バッハまでは、中全音律こそがヨーロッパの調律法だと言える。さらに、初期バロックまでの作品からは、鍵盤楽器に限らず、その他の楽器の音楽・声楽作品にも、中全音律を想定していると思われるものがある。オルガンは未だに中全音律で調律されていた。結局,中全音律は後から登場するウェル・テンペラメントとひとくくりにされる様々な音律が登場した後も併用され、12平均律音律が主流となる19世紀後半まで使い続けられた。』
『中全音律は、純正律に匹敵する美しい和音をもっていたが、それは限られた調性のみであり、その他の調性では実用性をもっていなかった。そのため,すべての調で使用できる調律法の模索が続けられた。』
『ウェル・テンペラメントはすべての調性で使える音律であるが、不等分音律であるために、調性によって表情が変わり(♯,♭が少ない調は和声的性格をもち、増えるにつれて旋律的性格に変化していくとも言われる)、それが音楽表現を豊かにするという特長をもっている。(音律を分類するため、このことを言葉で表現すると「調性的音律」となる。』
『最初に2の12乗根を精度高く計算し、それが使えるように計算結果を書物に著したのは、マラン・メルセンヌ(1588年~1648年:フランスの神学者・数学者)が「普遍的調和:音楽の理論と実際」(1636年)においてであった。この音律は, 16世紀頃からフレットをもつ弦楽器(リュー、,ギター、ヴィオラ・ダ・ガンバ)には使われていた可能性が高いが、 19世紀後半まで、多くの音楽家には受け入れられなかった。』
『中全音律のメリットは、やはり長3度の和音が美しく響くことである。やや狭い完全5度は僅かなビートが感じられるが、純正な長3度と合わせると十分美しく聞こえるし、むしろ柔らかい和声的輪郭を与えることに成功しているとも言える。ほとんど純正律に匹敵する、美しい和声をもった調律法である。 しかし、この音律はモーツァルト、ヘンデルをはじめとする多くの音楽家から愛され、 17世紀から19世紀にかけて広く用いられた。その事実、,特にウィーン古典派の作品は中全音律で演奏可能な調性で書かれたものが非常に多いことから見て取れる。また、「平均律クラヴィーア曲集」ではヴェルクマイスター調律を用いたと考えられるバッハが、その生涯で演奏したオルガンは中全音律で調律されたものであり、バッハは中全音律を認め受け入れていたことが窺い知れる。事実,バッハの大多数の曲は中全音律で演奏できる調性で書かれているし、そうでない場合、演奏者はその楽曲の適切な解釈をするために、わざわざその調性が選ばれた、それ相応の理由を見つけ出す必要があるのかもしれない。』
『16世紀半ばから19世紀にかけて、名の通った数学者・物理学者はたいてい音律問題に首を突っ込んでおり、すでに存在する音律の弱点を克服すべく新たな音律が次々と生み出されていたことはすでに述べたとおりである。実はその過程で、結局は12平均律音律が最もたやすく問題を解決する手段ではないかと考える音楽理論家が増えていった。また,次々と新たに生まれてくる楽曲では、より新しい響きの探求が行われ、そのため、それまで不協和音とみなされていた響きが、時の流れとともに心地よく感じられるようになったり、逆に、それまでの協和音が単純で物足りなく感じてしまうことも起こってきていた。つまり、人々は12平均律音律の長3度の濁りに対し慢性的な不感症になりつつあり、バッハの時代のオルガニスト達が苦痛の表情をもって感じたその濁りを、何の抵抗もなく快感的なハーモニーとして受け入れる土壌ができつつあったのである。』
※この著者によっても、「残響の多い教会で,たとえ単旋律の合唱であっても、前の音が残っている間に3度・4度・5度を取るので自然と純正律で歌っていたと考えられる」と純正律が誕生したことは教会の残響との関係を意識している。
1584年に朱載堉は「律学新説」の中で十二平均律を発表※ヨーロッパでの純正律の発生とほぼ同時期になる。
朱載堉音楽理論の思想的研究(田中 有紀) 東京大学大学院人文社会系研究科・文学部 https://www.l.u-tokyo.ac.jp/content/000000042.svg から引用、『本論文でとりあげるのは、世界で初めて十二平均律理論を発明した、明代後期の朱載堉(1536~1611年)である。』、『朱載堉は、これまでの儒者が三分損益法とよばれる理論に依拠し、楽律を計算してきたことを批判した。その著作『律学新説』1584年)の中で、新しい方法「新法密率」を提唱した。これが、現在の十二平均律理論にあたる。』、『清代に入ると、『律呂正義』など官製楽律書は、三分損益法の「往きて返らない」数の変化こそを「自然」とみなし、平均律は、あまりに整えられた「人為」であると判断した。朱載堉にとっての「自然」な世界は、緻密な「人為」によって構築された、いつわりの「自然」とみなされてしまったのである。』
※中国は12平均律が評価されなかったとのこと。鍵盤楽器が流行らなかったことと書いてあるが、中国の二胡はヴァイオリンと同じく、フラットがないので適度に調整ができると思われる。その中で合奏もできそうであるから、記録にはないが、現実の演奏で、純正律に合わせて演奏するような考え方を採用した可能性もあったかもしれない。
1692和算家の中根元圭が、「律原発揮」を表し、1オクターブを12乗根に開き12平均律を作る方法を発表